|
|
元のページへ戻る |
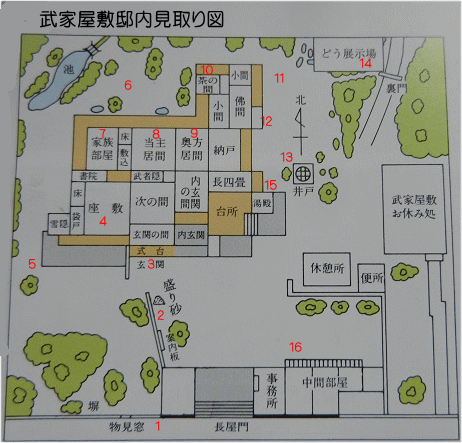 |
この武家屋敷は江戸時代に松江藩の中級藩士が 住んでいた屋敷です。 1733年(享保8)の大火で焼失した後に再建された 建物です。約280年前の古い姿で残されています。 六百石取りの藩士となれば、屋敷も大きなものです。 千葉県佐倉市内の武家屋敷は90~300石程度の武士の 屋敷なので、それと比べると部屋の数が多いです。 門構えも松江は長屋門になっています。 屋敷の中には上がれませんので、外周からの眺めのみと なりました。 赤数字は以下の写真の順序に従い付けています。 |
 |
① 塩見縄手にある武家屋敷の長屋門です。 敷地の大きさがよく判ります。 この屋敷は幕末に滝川家の屋敷となり、 明治の漢学者滝川亀太郎文学博士の 実家でした。 |
 |
② 門を入ると盛砂があります。 この砂は有事の際に刀で数回切りつけ、 いざと言う時に使えるようにするための 砂だそうです。 江戸時代には形式的なものに なっていたかもしれません。 |
 |
③ 式台玄関の内部です。 姫籠が展示してありました。 1650年(慶安3)松江藩家老の娘が 西光寺に嫁入りする際に使用した籠と 説明されています。 画面にポインターを置くと 玄関の建物をご覧いただけます。 この右隣に通用玄関がありますが、 中には入れません。 |
 |
④ 座敷です。10畳敷きの半間床が 付いています。 |
 |
⑤ 西よりの庭になります。 |
 |
⑥ 裏庭と私生活の部分です。 画面にポインターを置くと 庭側の眺めもご覧いただけます。 |
 |
⑦ 家族部屋で、家族が日常生活する 部屋です。玩具などが展示されて います。 |
 |
⑧ 当主の居間です。 当主が在宅の折に過ごす部屋です。 莨盆などの生活品が展示されています。 |
 |
⑨ 奥方の居間です。 手鏡や箪笥、衣装の展示があります。 |
 |
⑩ 茶の間です。 二畳に炉が切られています。 |
 |
⑪ 北東の庭に明治の漢文学者 滝川亀太郎文学博士の顕彰碑が 立っています。 この碑の碑文は吉川幸次郎が選び、 字は中国文学の小川環樹文学博士 (貝塚茂樹、湯川秀樹の弟)の筆になり、 石は香川県丸亀市青木産の自然石が 使われています。 滝川亀太郎博士は幕末(慶応元)より この屋敷で育ち、晩年には再びここに戻り、 1946年(昭和21)に81歳でなくなって います。 |
 |
⑫ 東側に面した部屋です。 右が小間、左が仏間になっています。 |
 |
⑬ 東の庭にある井戸です。 |
 |
⑭ 北東の奥にある「どう展示場」の 展示品、「鼕(どう)」です。 直径が150cm程あります。 松江では皮の径と胴の長さが 同じ程度の太鼓を「鼕」と呼び、 胴の長さが短いものを「太鼓」と 呼びならわしてきたそうです。 現在でも出雲地方の伝統行事には この名前が残っているそうです。 画面にポインターを置くと 祭りに使われる「鼕」の様子を ご覧いただけます。 |
 |
⑮ 中央が台所、右手少し張り出して 見えるのが湯殿です。 左の入口が勝手口になります。 甕が半分外に出ていますが、 井戸で汲んだ水をこちら側から注ぎ、 屋内の半分から汲むようになっています。 画面にポインターを置くと 台所の内部をご覧いただけます。 |
 |
⑯ 長屋門の「中間部屋」です。 |
| 元のページへ戻る |